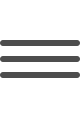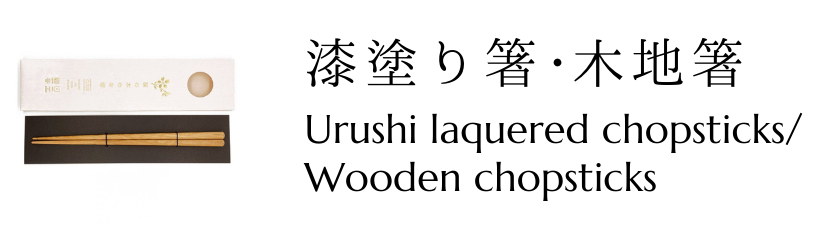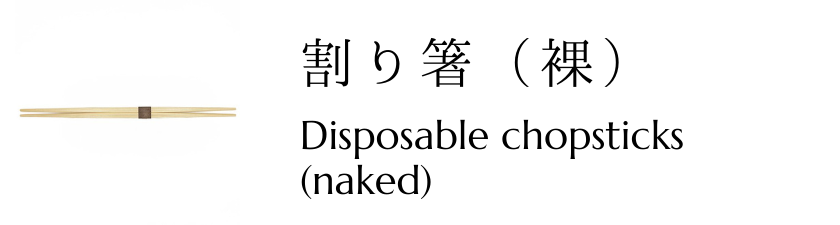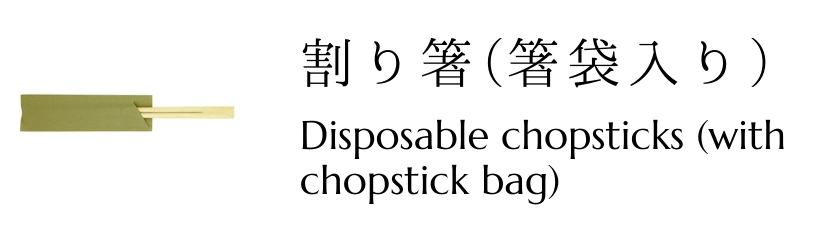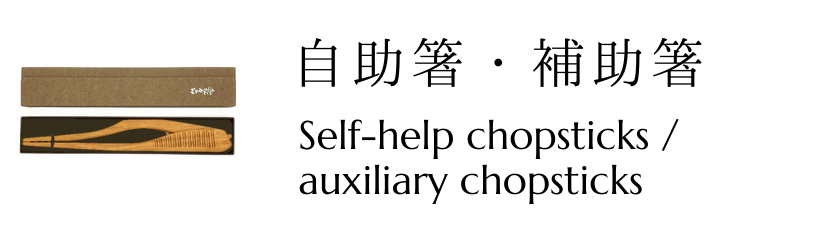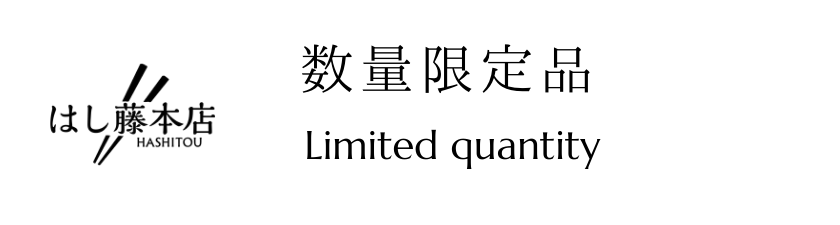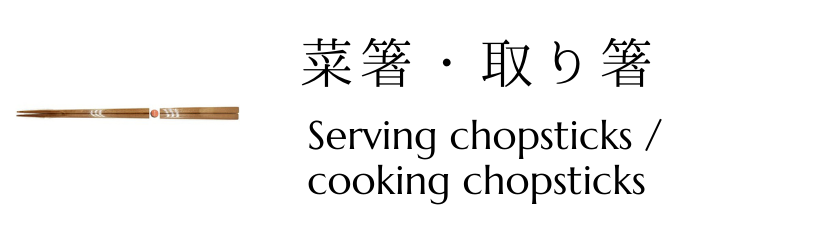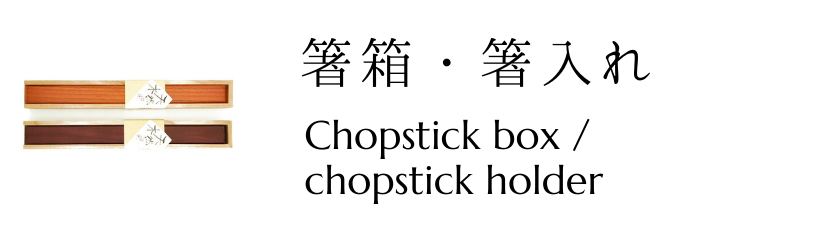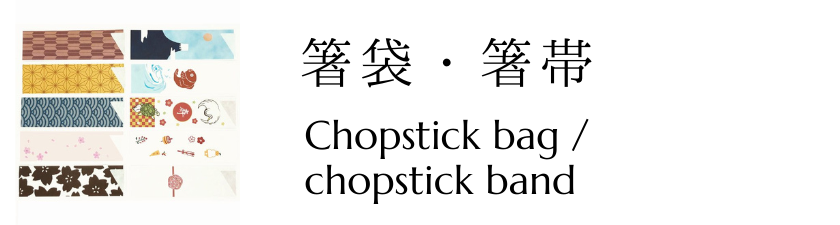「間伐材こそ環境に良い」は本当?
あなたは、
「間伐材こそ環境に良い」
「大きな木を伐るのは環境破壊」
そう思っていませんか?
実はそういう人、わりと多いです。
テレビでも大きな木を伐り倒すシーンを流して「環境破壊だ」と言いますし、大きな木が伐り倒されるとなんとなく「かわいそう」という気持ちが芽生えます。
それもよくわかります。
企業もそれを利用して
「環境にやさしい間伐材を使用」
と表記してアピールしています。
こうした映像や商品を目にするうちに、まるで間伐材を使用していない製品は環境破壊をしているかのような気持ちになってしまいます。
ですが、残念ながらそれは合っているようで合っていないのです。
それはなぜなのか、これからご説明します。
・間伐とは
そもそも間伐ってなんでしょうか?
「大きな木を育てるために、小さな木を間引きする」
なんとなくそんなイメージありませんか?
残念ながら、それだけでは不十分です。
間伐には大きく分けて3つあります。
いずれも、太陽光を地面まで届かせることが目的です。
太陽光が地面まで届く森の木は元気に育ちます。
1.大きな木を育てるために、小さな木を間引きする
2.小さな木を育てるために、大きな木を間引きする
3.決めた列の木を大小に関わらず間引きする
2.と3.については、もしかしたらご存じ無かったかもしれませんが、これらも大事な「間伐」の1つです。
では、なぜ1.のイメージばかりが先行してしまうのか。
それは、野菜やプランターでの植物栽培の際の間引きのイメージが強いからです。
だから「間伐」と聞くと1.のことだと思ってしまうのです。
1年で収穫が出来たり、花が咲いたりする野菜栽培やプランターでの植物栽培と違い、収穫までに50年や場合によっては100年もかかる“山の畑”である木の栽培は、木材需要や山の状態、木の状態に合わせて1.〜3.を組み合わせて育てていく必要があるのです。
・主伐とは
主伐(しゅばつ)とは間伐をして木を大きく育てた先、50年後〜100年後に訪れるゴールです。
つまり、収穫です。
植林した山は木の畑。
大きな木に育てて、そして伐採(収穫)するのが目的なんです。
もし、「大きな木を伐るのは環境破壊」なのだとすると、大きく育った野菜は環境破壊だから収穫せずに放置したほうが良いのか?ということになってしまいます。
でもそれではもったいないですし、その場所は翌年以降もずっと何も植えられないことになってしまいます。
農家さんも生活できなくなってしまいます。
木だって収穫しなければ、林業家さんは間伐材だけでは生活できないのです。
・皆伐とは
ここでもう1つ、非常に印象が悪い「皆伐(かいばつ)」についてご説明します。
間引きが目的の間伐に対し、みんな伐採してしまう皆伐。
それだけで印象は悪いですが、皆伐とは主伐の種類の1つです。
山の一部がごっそり抜け落ちたかのような風景は、誰しも見覚えがあるかと思います。
遠目で見ると禿げ山がなんとも言えない環境破壊感・・・。
でもこれにも理由があります。
皆伐して同じ場所に植栽して育てれば、また同じ時期に同じような大きさの木を「収穫」することができます。
山に入って植栽する作業も楽になります。
林業としての効率や、商品の安定供給のためにされている1つの方法なのです。
かつて、木造家屋(現在のような輸入材の木造ではなく、杉や桧のいわゆる日本家屋です)で木材の需要が大きかった時代は、皆伐も広範囲でされていました。
ところが木材需要が減少した現在では、そこに暮らす動物たちへの影響も考慮され、比較的狭い範囲での皆伐がされるようになっています。
木がたくさん伐られていると「=環境破壊」だと思ってしまいがちですが、メガソーラー発電のための用地確保やバイオマス発電のためのそれとはまったく違うということをぜひ知っていてください。
さて、ここまでお読みいただいて、「間伐材こそ環境に良い」というイメージはいかがでしょうか?
たしかに、小さな木を間引いた場合の間伐材は建築材としては不向きなので、それを使用している商品というのは環境に良いと言えなくもないです。
だからといって、“間伐材だからこそ”環境に良いということも実は無い、ということもおわかりいただけたかと思います。
間伐材か否かに関わらず、私たちが思い込みをなくして木を使うことこそが山を育み、山の循環を生むことになると思うのです。
林業家の皆さんは、自分が生きている間には収穫できないかもしれないのに苗を植えて、育てて、その後を引き継いだ次の世代かそのまた次の世代の林業家が収穫し、また次の世代のために植栽を行なっています。
木の需要が減ってしまった現在、日本各地の山にバイオマス発電所が建ちました。
山に放置された間伐材や枝がもったいないから発電の燃料にしようという発想ですが、残念ながらそんなものでは発電量は足りず、むやみやたらに伐っては燃やすを繰り返しています。
これらは有名なブランド杉やブランド桧の産地でさえ問題になっています。
ある有名なブランド杉の林業家さんは一面木が伐り倒された山を見ながら私たちにこう言いました。
「今ここから見渡せる山は3年以内に全部バイオマスの燃料にされるよ」
「それでいいんですか?」と聞くと
「そしたらまたおれが苗木を植えるよ」と。
何十年もかけて育てて、使われることなく燃料にされた杉の跡地に、年齢的にも50年後の収穫期には立ち会えないかもしれない、しかも次も使われるかどうかわからないのに、苗木をまた植える気持ちを考えると涙が出そうになりました。
メガソーラー発電のために山の斜面の木がみんな伐られて一面ソーラーパネルになっている場所も増えました。
どちらも「環境に良いから」という大義名分のもとに。
「環境に良い」って何なのでしょう?
私たち自身が一度立ち止まって考えてみることが必要なのかもしれません、イメージに惑わされることなく。
こちらも併せてお読みください
・日本人と箸
・はし藤本店で出会える木
・日本の割箸は絶滅危惧種
・箸えらび 5つのヒント
・漆のはなし