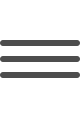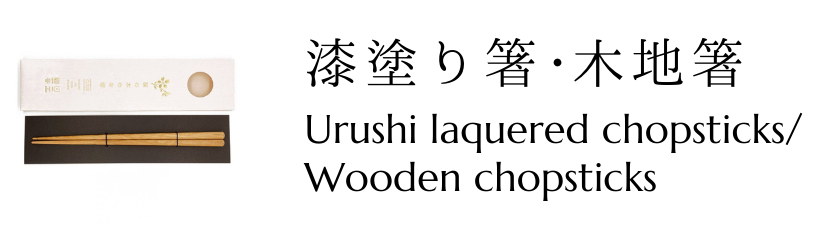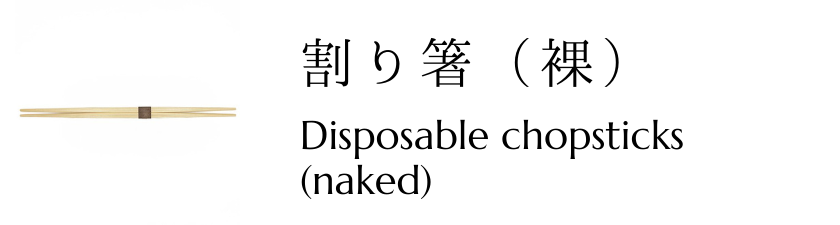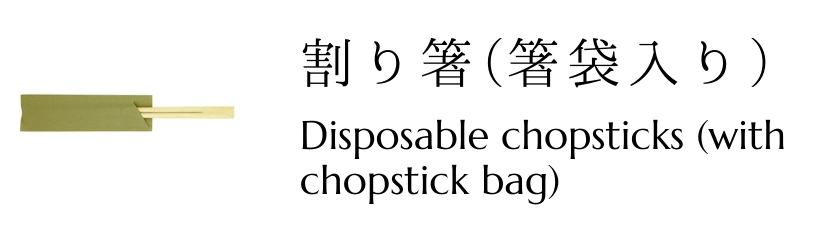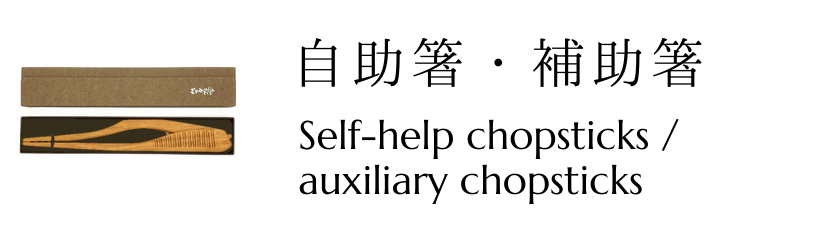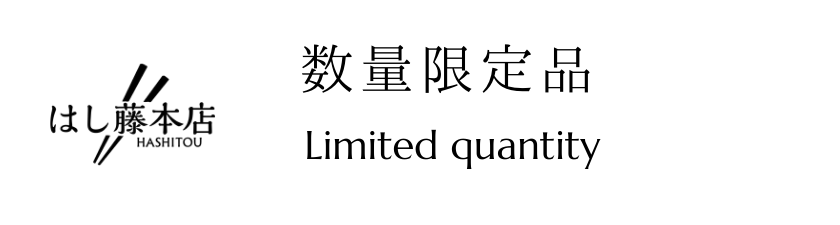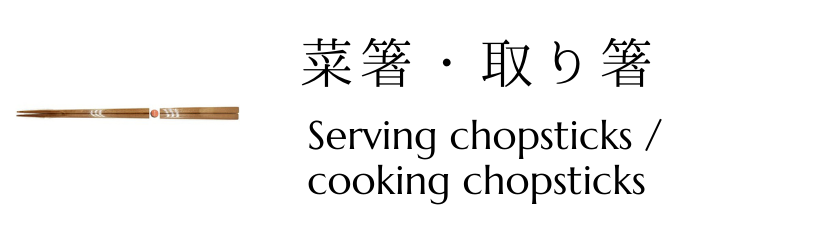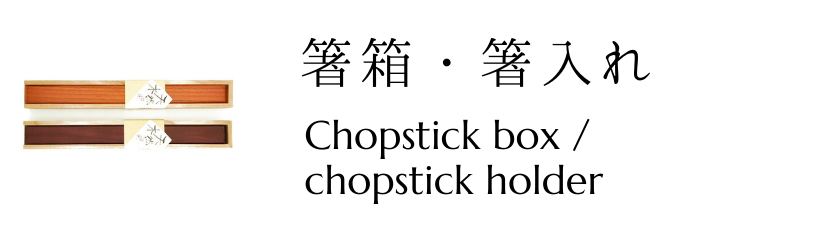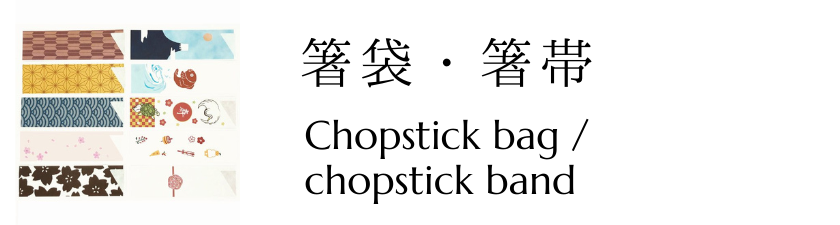箸えらび 5つのヒント
箸を選ぶうえで「これが正解」というものはありません、残念ながら。ですが、何を基準に選べば良いかわからないという方のために、5つほどヒントを・・・
1.長さ・太さ・重さ・形状で選ぶ
適切な箸の長さは、一咫半(ひとあたはん=親指と人差し指を直角に広げたときの親指の先から人差し指の先までの長さ×1.5)とか、手首から中指の先までの長さプラス3〜4cmくらいが目安とされます。
ですが、実際には手の大きさや厚み、持ち方のクセなどは人それぞれで、好みもそれぞれです。
四角なのか、五角なのか、それとも八角が持ちやすいのか。
それぞれ持ち比べてみてください。
そして、持ってみて動かしてみたときに箸先がぴったり合うことも重要です。

もちろんそれでも食事は出来るのですが、せっかくなら箸先で小さなゴマなどもつまめるほうが良くないですか?
是非ぴったりと箸先が合うものを選んでください。
ナタで割っただけの箸や、左右非対称の箸も実は持ちやすかったりもします。
たとえば、「箸アシメ」という商品があります。
これは下側に重みのある外国産材の鉄木、上側が軽い日本産の能登ヒバを使用しています。
形も鉄木が三角で能登ヒバが八角といびつですが、持ってみると安定感があり、箸の操作性も良いことがわかります。
また、どのくらいの重さが好みなのか。
どんな木を使っているかで重さも硬さも手触りもさまざまです。
たくさん持ってみて、自分に合う1膳を探してみてください。
2.木地の箸か漆塗りの箸か
木の温もりや自然の木目、香りなどがお好きなら木地の箸で、漆塗りのつややかさやしっとり感、デザインの多様性がお好きなら漆塗りの箸。
麺類や鍋物など、すべりやすい食べ物が好きなら木地で、口当たりの滑らかさなら漆塗り。
どちらも丁寧に使えば長く使えますが、漆塗りのほうが折れたりするリスクは低いです。
それでも曲がるときはあります、呼吸をする自然の木なので。
木の箸は汚れやすいと思われる方も多いのですが、洗ったあとに立てずに横にして乾かせば黒ずみが付きにくく、何年でも使えます。
菜箸や木のスプーンなども同様で、洗ったら必ず横にして乾かせば長持ちします。
3.料理で選ぶ
焼き魚などの細かい作業が必要な料理なら箸先が細いもの。
ラーメンやうどん、鍋物などすべりやすいものなら箸先が太くて四角いもの、なおかつ漆もウレタンも塗っていない木地がベスト。
細かい作業が必要なのに割箸のように箸先が太いものは食べづらく感じます。
逆にすべりやすくて重たいものなのに箸先が細いと力が要ります。
おすすめは箸先が太いものと細いものの2膳持ちです。
比較すると、食べ物によって使いやすさが全く異なるのがわかると思います。
1膳を休ませながら使うことで、箸も長持ちします。
4.産地・樹種・稀少性で選ぶ
重めな木が多い外国産材か、それとも国産材か。
はし藤本店は日本の木と職人を応援したいので、国産材を推しています。
輸入材の中には、黒檀や紫檀など箸の材料としては有名な木もありますが、日本の木にもさまざまな種類があります。
国産材ならどの地域のものか、応援したい地域の材で選ぶのもアリです。
漆塗りの産地にも、津軽には伝統的な塗りの手法があったり、川連(かわつら)はシンプルで堅牢な塗り、輪島は下地から手間をかけて塗り重ねているなど、それぞれに特徴があります。
木地の箸の中でも、水との親和性が良く、乾きが早いのは杉や桧といった針葉樹で、水が浸透しづらいのは広葉樹です。
また、いつ出会えるかわからない御蔵島の黄楊(つげ)・桑などの稀少材や、稀少材ではないものの、みかんやゆず、藪椿など木材としてはあまり流通しないもの、木目が面白いものなど、人とはちがう自分だけの箸を選ぶのもアリです。
5.デザインで選ぶ
箸は食べるための道具なのですが、毎日の楽しい食事を演出するための道具でもあります。
「この箸で食べるとおいしそう」
「テーブルコーディネートに合いそう」
「食事が楽しくなりそう」
「食事のときの手元の所作が美しく見えそう」
自分がアガるデザインで選ぶのもアリです。
もしそれが国産材なら私たちもうれしいです。
こちらも併せてお読みください