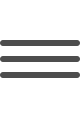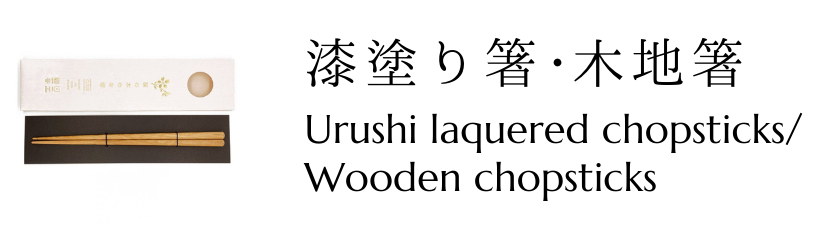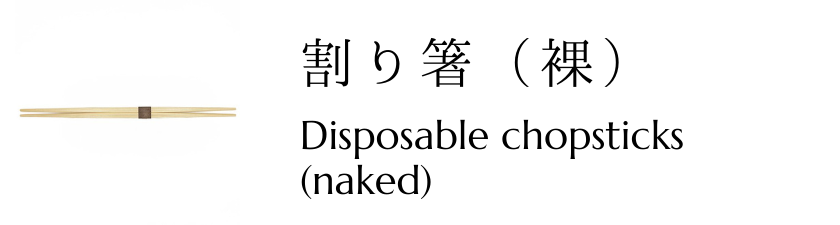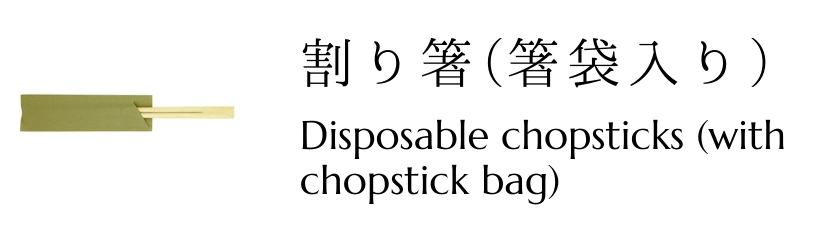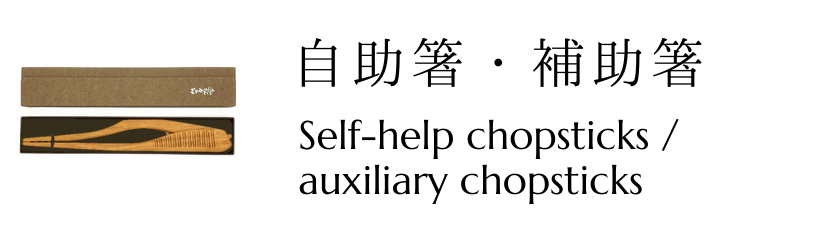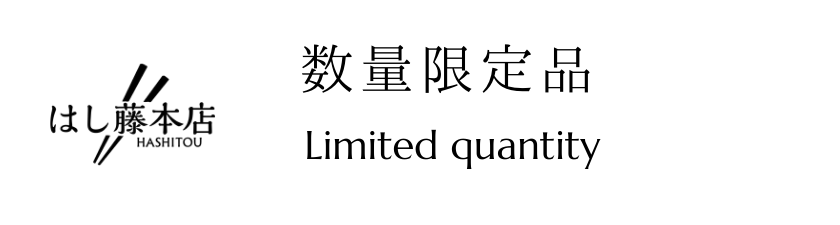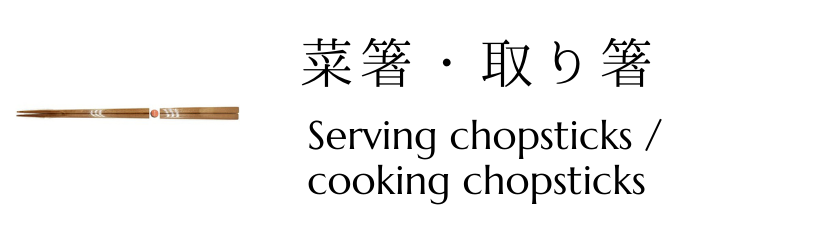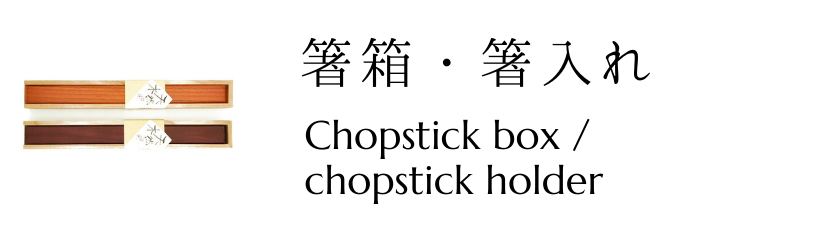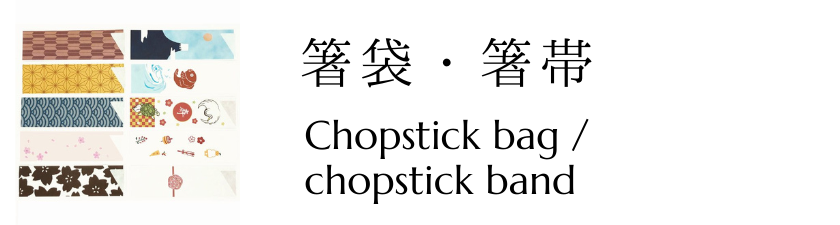- ホーム
- > 箸(塗り箸・木地箸)
- > 職人漆塗箸
Shopping Guide
返品について
- 返品期限
- 商品到着後7日以内とさせていただきます。
- 返品送料
- お客様都合による返品につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。交換の際には弊社からお送りする交換品の送料につきましてもお客様のご負担とさせていただきます。不良品に該当する場合は当方で負担いたします。
配送・送料について
- ヤマト運輸
-
【送料880円】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【送料1,430円】
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県 ・福井県・石川県・富山県・静岡県・山梨県・長野県・愛知県・岐阜県・三重県・和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県
【送料1,650円】
北海道・四国・九州・沖縄・その他離島
商品代金が5,500円(税込)以上の場合無料
海外発送不可
支払い方法について
- Amazon Pay
- Amazonのアカウントに登録された配送先や支払い方法を利用して決済できます。
- クレジットカード決済
-





- 代金引換
-
手数料:一律330円(税込)
商品代金が11,000円(税込)以上の場合無料
営業日について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
モバイルショップ


株式会社はし藤本店
〒111-0035 東京都台東区西浅草2-6-2
TEL:03-3844-0723 FAX:03-3845-6304
TEL:03-3844-0723 FAX:03-3845-6304